なぜパーソナルトレーニングは結果が出るのか?トレーナーが実践する効果を10倍にする思考法
目次
- はじめに:自己流トレーニングの「見えない壁」
- 第1章:結果を出すための土台作り – すべては「評価(アセスメント)」から始まる
- 第2章:オーダーメイドという言葉の真実 – プログラムデザインの思考法
- 第3章:1レップの質を極限まで高める – セッション中の思考法
- 第4章:トレーニング効果を24時間持続させる – ジム外での思考法
- 第5章:成長し続けるための羅針盤 – 継続と進化の思考法
- まとめ:あなたの時間は有限、だからこそプロの思考法を活用する

はじめに:自己流トレーニングの「見えない壁」
フィットネスへの関心が高まる現代、YouTubeやSNSを開けば、無数のトレーニング動画やダイエット情報が溢れています。「これなら自分でもできそうだ」と意気込んでジムに入会し、見よう見まねでトレーニングを始めてみたものの、数ヶ月経っても体に望むような変化が現れない…。それどころか、腰や肩に違和感を覚えたり、モチベーションが続かずにジムから足が遠のいてしまったり。
これは、決してあなただけが経験することではありません。多くの人が、努力や時間の不足ではなく、正しい知識と戦略の欠如という「見えない壁」にぶつかり、挫折していきます。頑張っているのに結果が出ない最大の理由は、情報が多すぎること、そしてその情報が「あなた自身」に最適化されていないことにあります。
Aさんに効果があった方法が、Bさんにも同じように効果があるとは限りません。骨格、筋力レベル、生活習慣、過去の怪我、そして心の状態。これら全てが複雑に絡み合い、一人ひとりの体は唯一無二の存在だからです。
では、なぜパーソナルトレーニングを受けると、多くの人が劇的な変化を遂げることができるのでしょうか?それは、単に「マンツーマンで教えてもらえるから」という表面的な理由だけではありません。その裏側には、科学的根拠に基づき、お客様一人ひとりを成功に導くための、プロフェッショナルな「思考法」が存在します。
この記事では、私たちパーソナルトレーナーが、お客様の結果を出すために日々どのような思考プロセスを辿っているのか、その舞台裏を余すところなく公開します。それはまるで、熟練のシェフが最高の料理を作るために、素材選びから火加減、盛り付けまで緻密に計算するプロセスに似ています。
この記事を読み終える頃には、「なぜパーソナルトレーニングは結果が出るのか」という問いに対する答えが明確になるだけでなく、あなたのトレーニング効果を飛躍的に高めるための「思考の型」を手に入れているはずです。自己流トレーニングの壁を打ち破り、あなたの努力を100%結果に結びつけるための旅を、ここから始めましょう。
第1章:結果を出すための土台作り – すべては「評価(アセスメント)」から始まる
多くの人がパーソナルジムに抱くイメージは、「たくましいトレーナーが隣で檄を飛ばしながら、厳しいトレーニングを課す場所」かもしれません。しかし、私たちの仕事は、いきなりトレーニングを始めることではありません。すべての始まりは、お客様を深く、多角的に「知る」ことから。つまり、「評価(アセスメント)」です。
私たちの思考法の一つ目は、「お客様という一冊の本を、細部まで丁寧に読み解く」というものです。この最初のステップを疎かにしては、決して最適なプログラムを作ることはできません。
なぜカウンセリングが重要なのか?
最初のカウンセリングは、単なる事務的な手続きではありません。お客様が口にする「痩せたい」「筋肉をつけたい」といった言葉の奥にある、本当の動機や願望(潜在的ニーズ)を探るための、極めて重要な対話の時間です。
「痩せてどうなりたいですか?」という問いに、「好きな洋服を自信を持って着たい」「健康診断の数値を改善して、家族を安心させたい」「子供の運動会で活躍できるパパになりたい」といった答えが返ってきます。この「なりたい未来の姿」こそが、長期的なモチベーションの源泉となります。私たちは、この目標の解像度を極限まで高めることで、お客様と二人三脚で進むための、揺るぎない北極星を設定するのです。
さらに、日々の仕事内容、食事のリズム、睡眠時間、ストレスレベルといったライフスタイル全体をヒアリングします。これにより、非現実的な計画ではなく、お客様の生活に無理なく溶け込む、継続可能なプランを設計するための土台が築かれます。
静的アセスメント:止まっている姿から体のクセを読む
カウンセリングの次は、お客様の現在の「体の状態」を客観的に評価します。まずは、ただ立っているだけの姿、つまり「静的姿勢」を分析します。前後左右から姿勢を観察することで、素人目には分からない多くの情報が読み取れます。
例えば、
・肩の高さが左右で違う場合、背骨の歪みや、左右の筋肉の不均衡が考えられます。
・骨盤が前傾している(反り腰)場合、腹筋群の弱化と背筋群や股関節前側の筋肉の過緊張が疑われます。これは腰痛の大きな原因となります。
・頭が肩より前に出ている(ストレートネック)場合、首や肩のこり、頭痛につながりやすく、背中のトレーニングの効果を阻害する可能性があります。
これらの情報は、どの筋肉を優先的に強化(活性化)し、どの筋肉を緩める(抑制する)べきかという、プログラムデザインの重要な指針となります。ただ鍛えるのではなく、「体のバランスを整えながら鍛える」という視点こそが、怪我を防ぎ、機能的で美しい体を作るための鍵なのです。
動的アセスメント:動いている姿から弱点を見抜く
次に、実際に体を動かしていただきながら評価を行います。これを「動적アセスメント」と呼びます。代表的なものに、自重でのスクワット動作があります。
お客様にスクワットをしていただくだけで、実に多くのことが分かります。
・しゃがんだ時に膝が内側に入る(ニーイン):お尻の筋肉(特に中殿筋)がうまく使えていない可能性があります。このままスクワットを続けると、膝を痛めるリスクが高まります。
・かかとが浮いてしまう:足首やふくらはぎの柔軟性が不足しています。これにより、フォームが崩れ、腰への負担が増大します。
・上半身が過度に前に倒れてしまう:体幹の筋力不足や、股関節の柔軟性の問題が考えられます。
これらの「エラー動作」は、お客様が本来持っているはずのパフォーマンスを制限している「弱点」です。私たちは、これらの弱点を特定し、それを改善するためのエクササイズ(コレクティブエクササイズ)を本来のトレーニングプログラムに組み込みます。
このように、徹底したアセスメントを行うことで、私たちは初めて、お客様だけの「体の取扱説明書」を手に入れることができます。アセスメントなしにトレーニングを始めるのは、目的地の分からない海に、地図も羅針盤も持たずに出航するようなものです。この緻密な初期評価こそが、パーソナルトレーニングが最短で結果を出せる、一つ目の大きな理由なのです。
第2章:オーダーメイドという言葉の真実 – プログラムデザインの思考法
アセスメントによってお客様の現在地と目的地が明確になったら、次はその道のりを描く「プログラムデザイン」のフェーズに移ります。ここで重要になるのが、私たちの二つ目の思考法、「私たちは『点』ではなく『線』でプログラムを設計する」という視点です。
「オーダーメイド」と聞くと、単にその日の体調に合わせて種目を調整するような、場当たり的なものを想像するかもしれません。しかし、真のオーダーメイドプログラムは、数ヶ月先を見据えた、戦略的かつ長期的な視点で構築されています。
原理原則の適用:トレーニング科学の普遍的なルール
私たちのプログラムデザインは、長年の研究によって確立されたトレーニング科学の「原理・原則」に基づいています。これらは、誰にでも当てはまる普遍的なルールであり、プログラムの根幹を成します。
・特異性の原則:体は与えられた刺激に対して特異的に適応する。つまり、速く走りたいなら走る練習を、重いものを持ちたいなら重いものを持つ練習をする必要があります。目標に直結するトレーニングを選択する、という基本中の基本です。
・過負荷の原則:体を成長させるには、日常でかかる以上の負荷(ストレス)を与える必要がある。いつも同じ負荷では体は慣れてしまい、成長は止まります。
・漸進性の原則:過負荷は、急激ではなく少しずつ(漸進的に)高めていく必要がある。急激な負荷増加は、怪我のリスクを高めるだけです。
これらの原則を、アセスメントで得られたお客様個人の情報(目標、体力レベル、体のクセなど)と掛け合わせることで、初めて真に効果的なプログラムが生まれます。
「あなただけ」のプログラムはどう作られるか?
長期的なプログラムデザインは、大きな時間軸から小さな時間軸へと具体化していくプロセスを辿ります。
ステップ1:目標から逆算した期間設定(マクロサイクル)
まず、カウンセリングで設定した最終目標(例:3ヶ月で体脂肪率を5%減らす)を達成するための、全体の期間を設定します。これを「マクロサイクル」と呼びます。この期間全体で、どのような体の変化を、どのようなペースで起こしていくかの大まかな計画を立てます。
ステップ2:期間を分割し、中期的なテーマを設定(メゾサイクル)
次に、3ヶ月というマクロサイクルを、1ヶ月ごとの「メゾサイクル」に分割します。そして、それぞれのメゾサイクルに具体的なテーマを設定します。
・1ヶ月目:基礎期(正しいフォームの習得、神経系の適応、弱点改善)
・2ヶ月目:発展期(重量やボリュームを増やし、本格的な筋肥大・筋力向上を目指す)
・3ヶ月目:ピーク期(ダイエット目標であれば、食事管理と組み合わせ、脂肪燃焼を最大化)
このように期間を区切ることで、段階的にレベルアップしていくことができ、停滞を防ぎます。これを「ピリオダイゼーション(期分け)」と呼び、アスリートのコンディショニングにも用いられる、極めて効果的な手法です。
ステップ3:日々のトレーニング内容を具体化(マイクロサイクル)
最後に、1ヶ月というメゾサイクルを、1週間単位の「マイクロサイクル」に落とし込みます。ここで初めて、「月曜日は上半身の日、木曜日は下半身の日」といった具体的なトレーニングスケジュールや、各種目のセット数、レップ数などが決定されます。
種目選択のロジック:なぜその種目を選ぶのか?
マイクロサイクルにおける種目選択にも、明確なロジックがあります。
アセスメントで「お尻の筋肉が弱い」と判断されたお客様には、ただスクワットを処方するのではなく、まずはお尻の筋肉を目覚めさせるための「ヒップスラスト」や「クラムシェル」といった種目をウォーミングアップに取り入れます。
「反り腰」が顕著な方には、腰に負担のかかりやすい種目を避け、腹筋群を強化し、もも裏の柔軟性を高める種目を優先的に組み込みます。
このように、一つひとつの種目選択には、「なぜ今、あなたにこの種目が必要なのか」という明確な理由が存在するのです。
数値設定の科学:レップ数、セット数、インターバルに隠された意図
「10回3セット」という言葉をよく耳にすると思いますが、なぜ10回なのか、なぜ3セットなのかを考えたことはありますか?これらの数値設定も、科学的根拠に基づいて目標別に最適化されます。
・筋肥大が目的なら:8〜12回が限界となる重量で、3〜4セット。インターバルは60〜90秒。筋肉に代謝的ストレスを与え、成長ホルモンの分泌を促します。
・筋力向上が目的なら:1〜5回が限界となる高重量で、3〜5セット。インターバルは3〜5分。神経系の適応を促し、最大筋力を高めます。
私たちは、お客様のその日のコンディションを見ながら、これらの数値を微調整し、常に最適な刺激を与え続けます。
このように、パーソナルトレーニングのプログラムは、長期的な視点と科学的根拠に基づいた、緻密な戦略の結晶です。この「線」で考える思考法こそが、お客様を着実にゴールへと導く、二つ目の理由なのです。
第3章:1レップの質を極限まで高める – セッション中の思考法
完璧なプログラムをデザインしたとしても、それが正しく実行されなければ絵に描いた餅です。週に1〜2回のセッションの価値は、その時間内で行われる一回一回の動作(レップ)の質にかかっています。ここで重要になるのが、私たちの三つ目の思考法、「私たちは『10回の作業』ではなく『最高の1回』を10回繰り返す」というアプローチです。
自己流トレーニングでは、回数をこなすことが目的化しがちです。しかし、プロの視点では、たとえ10回の動作であっても、そのすべてが同じ価値を持つわけではありません。1回目から10回目まで、すべてのレップに意味があり、そこには緻密な観察と介入が存在します。
リアルタイムのフォーム修正
私たちの目は、お客様の動きをミリ単位で捉える、高性能なモーションキャプチャシステムのようなものです。お客様が動作を始めると同時に、私たちの頭の中では、理想的なフォームと目の前の動きを瞬時に比較・分析しています。
・「スクワットで少し膝が内側に入り始めたな。これは中殿筋の疲労のサインかもしれない。次のセット前にもう一度活性化させよう」
・「ベンチプレスで肩がすくんでいる。これは大胸筋ではなく、肩の三角筋前部で挙げようとしている証拠だ。『胸を張って、肩甲骨を寄せる』という意識をもう一度伝えよう」
・「デッドリフトのフィニッシュで腰を反りすぎている。これは腰を痛めるリスクがある。お尻をキュッと締める感覚を、触覚(タッピング)で伝えてみよう」
このような微細なエラーをその場で即座に修正することで、毎回のレップが、ターゲットの筋肉に的確にヒットする「質の高い1回」に変わります。この積み重ねが、自己流との間に圧倒的な差を生むのです。
「効かせる」ためのキューイング
ただ「もっと膝を曲げて」「背中を丸めないで」と指示するだけでは、お客様の動きは変わりません。プロのトレーナーは、お客様が体の感覚を掴めるような、巧みな言葉がけ(キューイング)を使い分けます。
・外在的キュー:「床を強く蹴って立ち上がる」「バーを天井に突き刺すように」といった、体の外にあるものに意識を向けさせる言葉。動きそのものをスムーズに引き出す効果があります。
・内在的キュー:「お尻の筋肉を固くする意識で」「背中の筋肉でバーを引き寄せる」といった、体内部の筋肉に意識を向けさせる言葉。マインドマッスルコネクションを高めるのに有効です。
お客様のタイプや種目の特性に合わせて、最適なキューイングを選択し、時には「薄いガラスを挟むように、ゆっくりとコントロールして下ろしましょう」といった比喩表現も用います。この言葉の力で、お客様の脳と筋肉の繋がりを強化し、「効いている」という感覚を最大限に引き出すのです。
限界を超えるための心理的サポート
トレーニングで最も成長が促されるのは、心身ともに「もうダメかもしれない」と感じる、限界付近の最後の数回です。自己流では諦めてしまうこの領域に、安全かつ効果的に踏み込ませるのが、パーソナルトレーナーの重要な役割です。
私たちは、お客様の表情、呼吸のリズム、動作の速度から、その日の限界点を正確に見極めます。そして、
・「あと2回、絶対にできる!フォームは崩れていない!」(ポジティブな声がけ)
・「大丈夫、万が一の時はしっかり補助に入りますから、安心して挙げてください」(安全性の担保)
・「この1回が、あなたの体を変えます!」(目的意識の再確認)
といった言葉で、心理的な壁を取り払います。
この絶妙なタイミングでのサポートにより、お客様は自分一人では到達できなかった領域に足を踏み入れ、筋肉に今まで以上の刺激を与えることができます。これは、単なる根性論ではなく、お客様のポテンシャルを100%引き出すための、計算された心理的アプローチなのです。
セッション中の60分間は、ただの運動時間ではありません。それは、科学と心理学を駆使した、お客様の体を最適化するための、極めて濃密な対話の時間です。この「最高の1回」へのこだわりこそが、パーソナルトレーニングの価値を決定づける、三つ目の思考法です。
第4章:トレーニング効果を24時間持続させる – ジム外での思考法
週に1〜2回、合計2〜3時間のトレーニング時間。これは、1週間(168時間)のうち、わずか2%にも満たない時間です。もし、このトレーニング時間だけで体が変わると考えているなら、それは大きな間違いです。本当の戦場は、ジムの外にある残りの98%の時間、つまり日常生活の中にあります。
ここで重要になるのが、私たちの四つ目の思考法、「お客様の体を24時間、365日体制でマネジメントする」という視点です。私たちの役割は、ジムの中だけで完結するインストラクターではなく、お客様のライフスタイル全体をより良い方向へ導く、伴走者でありコーチなのです。
「食事指導」ではなく「食習慣の最適化」
「体はキッチンで作られる」という言葉がある通り、トレーニング効果は食事によって大きく左右されます。しかし、私たちは一方的に「鶏むね肉とブロッコリーだけを食べなさい」といった、実行不可能な食事制限を課すことはありません。それは「指導」ではなく、お客様の生活を無視した「命令」だからです。
私たちの思考は、「食事指導」から「食習慣の最適化」へとシフトしています。
・現状の把握:まず、お客様に数日間の食事記録をつけていただき、現在の食生活の傾向(良い点・改善点)を客観的に分析します。
・小さな成功体験の積み重ね:いきなり全てを変えるのではなく、「まずは毎朝の菓子パンを、プロテインとバナナに変えてみませんか?」といった、負担の少ない「ベビーステップ」から提案します。この小さな成功体験が、次のステップへの自信とモチベーションにつながります。
・知識の提供と選択肢の提示:コンビニでランチを選ぶ際のポイント、外食や飲み会でのメニュー選びのコツ、太りにくい間食の選び方など、お客様が日常生活の中で「自分で考えて選べる」ようになるための知識を提供します。これにより、トレーナーがいなくても、お客様自身が自分の体をコントロールできるようになります。
私たちの目標は、お客様を食事制限で縛り付けることではなく、一生使える食の知識(食育)を提供し、健康的で持続可能な食習慣を築いてもらうことなのです。
休息と睡眠の重要性:超回復をデザインする
筋肉は寝ている間に作られます。トレーニングによって傷ついた筋繊維は、質の高い睡眠中に分泌される成長ホルモンによって修復・強化されるのです。いくらハードなトレーニングをしても、睡眠不足ではその効果は半減してしまいます。
そこで私たちは、睡眠の質を高めるための具体的なアドバイスも行います。
・就寝前のルーティン:就寝1〜2時間前に入浴して深部体温をコントロールすること、寝る前のスマートフォンの使用を控えること、リラックス効果のあるストレッチを取り入れることなどを提案します。
・睡眠環境の整備:寝室の温度や湿度、光や音のコントロールなど、睡眠の質に影響を与える環境要因についてもアドバイスします。
トレーニング(破壊)と、食事・睡眠(創造)は、車の両輪です。私たちは、この両輪がうまく回るように、お客様のライフスタイル全体を俯瞰してサポートします。
日常生活にトレーニングの視点を組み込む
私たちの思考は、日常生活のあらゆる動作をトレーニングの機会と捉えます。
・姿勢の意識:「デスクワーク中、1時間に1回は立ち上がって、胸を張るストレッチをしましょう。これだけで肩こりが改善され、トレーニングのパフォーマンスも上がります」
・NEAT(非運動性熱産生)の向上:「エレベーターではなく階段を使う」「一駅手前で降りて歩く」といった、日常生活の中での活動量を増やす意識づけを行います。この小さな積み重ねが、1日の総消費カロリーを大きく左右します。
このように、トレーニングの視点を日常生活にインストールすることで、ジムにいない時間も、お客様の体は少しずつ良い方向へと変化し続けます。この24時間体制のサポート体制こそが、トレーニング効果を最大化し、リバウンドを防ぐ、四つ目の思考法なのです。
第5章:成長し続けるための羅針盤 – 継続と進化の思考法
素晴らしいプログラムを作成し、質の高いセッションを提供し、24時間のサポートを行ったとしても、それが一過性のもので終わってしまっては意味がありません。人間の体は、良くも悪くも「適応」する生き物です。停滞期を乗り越え、モチベーションを維持し、長期的に成長し続けるためには、常に計画を見直し、進化させていく必要があります。
ここで登場するのが、私たちの五つ目の思考法、「私たちは『計画者』であると同時に、柔軟な『航海士』である」という考え方です。最初に立てた航路図(プログラム)は絶対的なものではありません。変化する風向きや潮の流れ(お客様の体の変化や心の状態)を敏感に察知し、臨機応応変に舵を取りながら、目的地へと船を進めていくのです。
データに基づいた客観的な進捗管理
私たちの判断は、感覚や憶測だけに頼るものではありません。定期的に体重、体脂肪率、体のサイズ(ウエスト、ヒップ、胸囲など)を測定し、トレーニングの使用重量やレップ数の記録を詳細につけます。これらの客観的なデータを分析することで、プログラムが順調に進んでいるのか、あるいは何らかの修正が必要なのかを正確に判断します。
お客様にビフォーアフターの写真を見比べていただくことも、極めて有効です。体重計の数字の変化は小さくても、写真を見れば、姿勢の改善や体の引き締まり具合といった「見た目の変化」が一目瞭然です。この視覚的なフィードバックは、お客様のモチベーションを劇的に高める効果があります。
停滞期(プラトー)を「成長のサイン」と捉える
どんなに順調でも、必ず訪れるのが停滞期です。自己流の場合、ここで「自分の限界はここまでか」と諦めてしまうことが多いのですが、私たちはこれを「体が最初の刺激に適応した、喜ばしい成長のサイン」と捉えます。
そして、このサインを察知した時こそ、私たちの腕の見せ所です。
・変数を変える:重量、レップ数、セット数、インターバル、種目の順番、トレーニングのテンポなど、様々な変数に変化を加えることで、体に新たな刺激を与えます。
・高強度テクニックの導入:ドロップセットやスーパーセットといった、より強度の高いトレーニングテクニックを導入し、筋肉の適応能力のさらに上を行く刺激を与えます。
・ディロード(積極的休養)の提案:意図的にトレーニングの負荷を下げる期間を設け、疲労した神経系や関節を回復させます。この戦略的な休息が、その後の爆発的な成長につながることが多々あります。
停滞期は壁ではなく、次のステージへ上るための「階段」です。私たちは、その階段を上るための最適な方法を、豊富な知識と経験の中から選択し、お客様に提示します。
モチベーションの科学:続けるための仕組み作り
体の変化だけでなく、心の変化に寄り添うことも、私たちの重要な役割です。仕事のストレス、家庭の事情、一時的な体調不良など、モチベーションが低下する要因は無数にあります。
私たちは、心理学的なアプローチも用いて、お客様がトレーニングを「続けられる仕組み」を一緒に作ります。
・目標の再設定:長期的な目標に加え、「来週までにこの重量をクリアする」といった短期的な目標を設定し、達成感を頻繁に味わえるようにします。
・成功体験の言語化:「最初はできなかった懸垂が、補助ありでできるようになったじゃないですか!」「このパンツ、ゆるくなりましたね!」といった具体的な成長を言葉にして伝え、お客様の自己効力感を高めます。
・予約という「コミットメント」:パーソナルトレーニングの予約そのものが、「ジムに行く」という行動を促す強力な仕組みになります。一人ではサボってしまいそうな日でも、トレーナーが待っていると思えば、自然と足がジムに向かいます。
私たちは、お客様の最も身近な理解者であり、時には厳しく、時には優しく励ますコーチとして、ゴールまで伴走し続けます。この継続と進化を支える柔軟な思考法こそが、一度掴んだ成果を揺るぎないものにする、最後の鍵なのです。
まとめ:あなたの時間は有限、だからこそプロの思考法を活用する
これまで、パーソナルトレーニングがなぜ圧倒的な結果を出せるのか、その裏側にある5つの思考法を解説してきました。
- 評価の思考法:お客様という本を読み解き、現在地と目的地を正確に把握する。
- プログラムデザインの思考法:「点」ではなく「線」で考え、長期的かつ戦略的な計画を立てる。
- セッション中の思考法:「最高の1回」を繰り返し、トレーニングの質を極限まで高める。
- ジム外での思考法:24時間体制でお客様のライフスタイルをマネジメントし、効果を持続させる。
- 継続と進化の思考法:データと対話に基づき、停滞を乗り越え、成長し続けるための舵取りを行う。
これらは、決して魔法ではありません。解剖学、生理学、栄養学、心理学といった科学的根拠に基づいた、極めて論理的なプロセスの積み重ねです。
自己流のトレーニングは、広大な海を手漕ぎボートで、当てずっぽうに進むようなものです。運が良ければ目的地にたどり着くかもしれませんが、多くの時間と労力を費やし、途中で遭難してしまうリスクも低くありません。
一方、パーソナルトレーニングは、経験豊富な航海士(トレーナー)が、高性能なエンジンと最新の航海計器を備えた船(科学的メソッド)で、あなたを最短かつ最も安全な航路で目的地までエスコートするようなものです。
あなたの時間は、何にも代えがたい貴重な資産です。その貴重な時間を、遠回りや試行錯誤に費やすのではなく、最短で最高の結果を得るために投資してみませんか?
もし、あなたが今、自己流トレーニングの「見えない壁」の前で立ち止まっているのであれば、ぜひ一度、私たちのジムの扉を叩いてみてください。私たちが持つプロフェッショナルな思考法のすべてを駆使して、あなたがまだ見ぬ「最高の自分」に出会うためのお手伝いをさせていただくことを、心からお約束します。
投稿者プロフィール

-
MMTパーソナルジム静岡代表
【所有資格】
・メンタルトレーニングスペシャリスト
・心理カウンセリングスペシャリスト
・スポーツフードスペシャリスト
・マインドフルネスコンサルタント
・メンタルヘルススペシャリスト
・ファスティングスペシャリスト
【経歴】
・トレーナー歴24年
・2023ベストボディ静岡大会モデル部門ファイナリスト
・2024年ベストボディ静岡大会モデル部門6位
【詳細】
・スポーツクラブでのインストラクター歴14年
フィットネス部門のトップとして活動。ダイエット指導やボディメイク以外にも生活習慣病予防プログラム、介護予防指導、スタジオプログラム、スイミング指導の経験も豊富。
・パーソナルジムでの代表トレーナー歴10年
クライアントには弁護士、医師、歯科医師、看護師、税理士、企業の代表取締役など多数おり、50代マラソン全国ランキング3位の方の指導も行っている。
最新の投稿
 未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み
未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み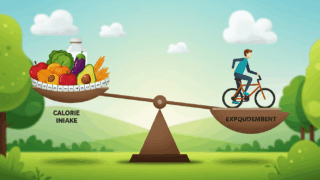 未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識
未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識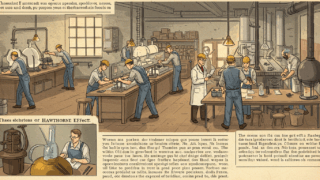 メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある
メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある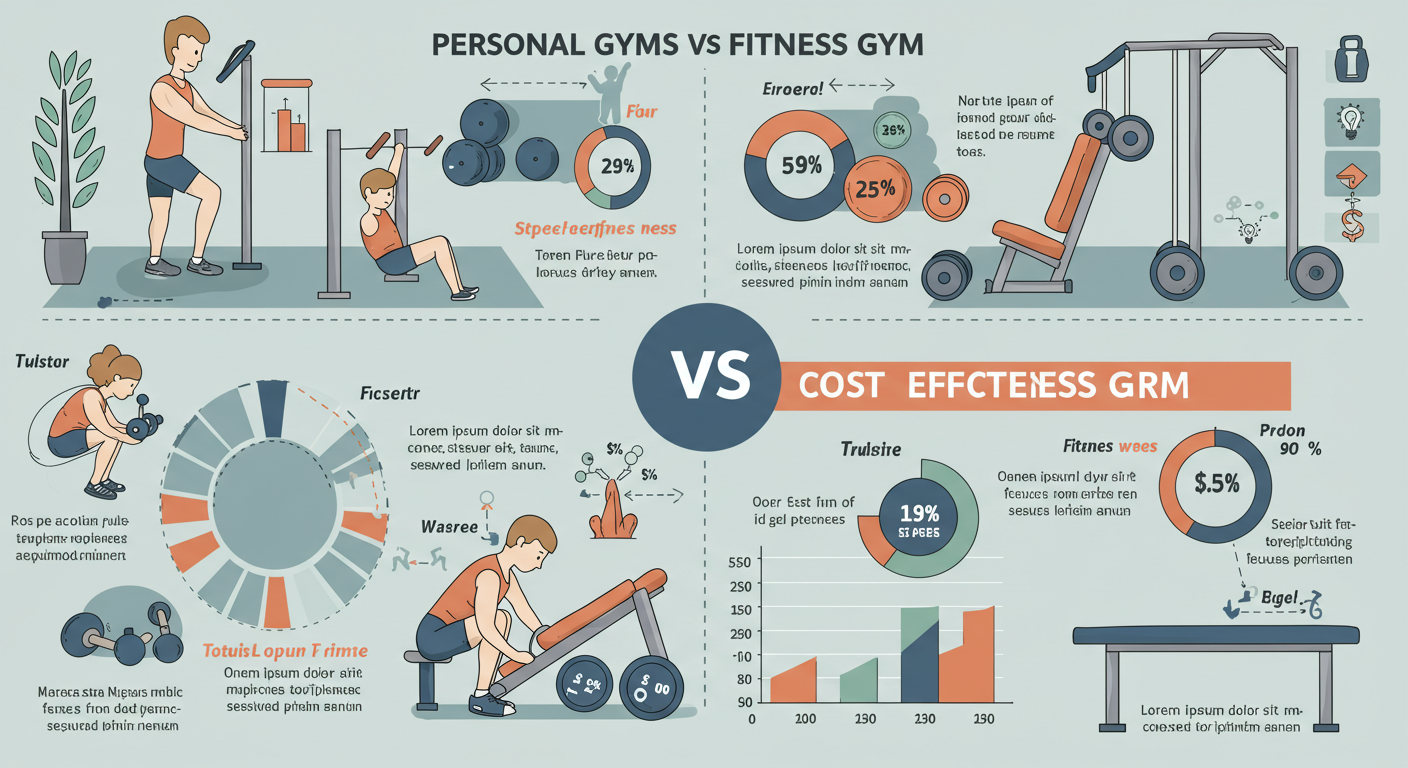 未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】
未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】


